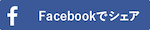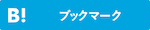【アジア・ユニークビジネス列伝】
日本がモデルの「道の駅」(インドネシア)
世界初「魚の切り身」培養(シンガポール)
それを売るのか、そんなサービスがあるのか。アジアでは思いもよらない商品やサービスに出会う。現地ならではのユニークなビジネスから今回は、日本をモデルに開発した「道の駅」と、ハタやウナギなどの魚肉を培養する最新技術を紹介する。
【インドネシア】
日本モデル「道の駅」
スラウェシ島に続々

建物は日本とスラウェシ北部の民族「ミナハサ」の伝統建築様式を融合させた設計。名称のパケワとは、9~10月ごろが旬の日本の梅に似た果実。同駅の製品担当者は「将来的にはパケワの実を使った商品を開発したい」と夢を描く=5月、インドネシア・北スラウェシ州トモホン市(NNA撮影)
インドネシアのスラウェシ島北部で、日本をモデルにした「道の駅」がオープンした。国際協力機構(JICA)の支援事業として、千葉県第1号の道の駅を運営する「ちば南房総」(同県南房総市)と南房総市が協力。地域の農業や観光業の振興につなげる。
「道の駅PAKEWA(パケワ)」は5月26日、北スラウェシ州の州都マナド市から車で約1時間のトモホン市に開業。マナドは海の観光地として有名だが、人口約10万のトモホンは冷涼な避暑地で高原野菜や菊などを代表とする花の産地として知られる。
パケワでは、菊など生花の鉢植えや贈答用の花かご、地場産オーガニック野菜、パームシュガーを使った菓子など、50の中小事業者や個人事業主が手掛ける商品を扱う。トモホンコーヒーを販売するカフェ、焼き肉やしゃぶしゃぶを提供する居酒屋も併設している。

店内では名産のトモホンコーヒーを販売しているほか、居酒屋も併設する=5月、インドネシア・北スラウェシ州トモホン市(NNA撮影)
冷涼な高原地域という地の利を生かして有機野菜づくりを手がける農家は「花にも引けを取らない野菜があると伝えたい」と意欲的だ。農家のヘルさん(42)は、レストランチェーンにパプリカなどの野菜を卸していたが、道の駅で直売するようになり、売値を2~3割高く設定できるようになったと話す。「出店する農家が増えれば地元の農業がもっと活性化するはずだ」と期待を寄せる。
道の駅は、JICAの「草の根技術協力」事業として整備。1993年、南房総市で開業した「道の駅とみうら 枇杷倶楽部(びわくらぶ)」の初代所長を務めた加藤文男氏がプロジェクトリーダーに就任した。加藤氏は、農産物の品質管理を徹底してブランド化することを提案。直売や契約栽培に取り組みながら、消費者の嗜好(しこう)に合わせた栽培体系を構築することもアドバイスした。
トモホン市の農家はこれまで販路が限られていた上に、仲買人を通して農産物を売買するため買い取り価格を低く抑えられていた。だが、道の駅で直売することで「ようやく自分たち農家が売値を付けられる段階まできた」(加藤氏)。農家が消費者の嗜好(しこう)に配慮しながら、安全で健康的な農産物を作れるような力を付けてきたという。
日本式の道の駅は、インドネシアではトモホン市が2カ所目。第1号は、2018年に南スラウェシ州バンタエン県で建設された。こうした日本式の道の駅は、東南アジアを中心に世界でも広がりつつある。JICAの支援事業では09~10年、ベトナムでの開業が最初のケースだ。
スラウェシ島では、他にも南スラウェシ州で道の駅2件の計画が進行中だ。同州開発局の関係者によれば、州南部のジェネポント県では飲食店5店の施設が先行営業を限定的に開始した。中部のシデレン・ラッパン県でも建物はほぼ完成しており、年内のオープンを目指す。【山本麻紀子】

トモホン市出身で、パケワの代表を務めるヴォニーさん。「トモホンのポテンシャルを高めて、魅力を住民や観光客にもっと伝えたい」と熱く語る=5月、インドネシア・北スラウェシ州トモホン市(NNA撮影)

道の駅で販売している新鮮なオーガニック野菜。「女性客に手に取ってもらえるように、清潔なパッケージ包装を心がけた」と関係者=5月、インドネシア・北スラウェシ州トモホン市(NNA撮影)
【シンガポール】
世界初「魚の切り身」培養
希少ウナギも「皮ぱりっと」

イスラエルのステーキホルダーとシンガポールのウマミ・ミーツは共同で、魚の培養細胞から「切り身」を製造することに成功した(ウマミ・ミーツ提供)
イスラエルとシンガポールの企業が、食品の3Dプリント技術を用いた魚の「切り身」を共同開発した。魚の培養細胞を利用して切り身全体を再現したのは世界初という。3D印刷で成形された切り身製品の商用化に向けた大きな一歩となる。
培養肉製品の開発・製造を行うイスラエルのステーキホルダー(Steakholder)・フーズと、シンガポールのフードテック(先端食品技術)企業ウマミ・ミーツが開発を手掛けた。ステーキ社は、独自の3Dバイオプリント(培養細胞で3D印刷する食品再現技術)を活用し、さまざまな種類の培養肉や培養シーフード製品を開発している。ウマミ・ミーツは、ウナギをはじめとする希少魚・高級魚の培養肉の開発・製造を専門とするフードテック企業だ。
両社は4月下旬に試作品を発表。ステーキ社は、ハタの培養細胞をウマミ・ミーツから提供してもらい、独自の3Dバイオプリント技術を用いてハタの切り身を再現した。
規制当局への関連書類を2024年初頭に提出し、許可が下り次第、生産を開始する。まずアジア市場向けの製品を、食品メーカーと協業して製造・販売する計画だ。
ウマミ・ミーツのミヒル・ペルシャド最高経営責任者(CEO)はNNAに対して「製品の詳細は今年後半に公表する予定だ」と述べた。ステーキ社のアリク・カウフマンCEOは「他の魚の培養細胞も使用できるよう協業関係を拡大していきたい」と語った。
焼いたウナギの皮
ぱりっと感を再現
ウマミ・ミーツは、ニホンウナギなど希少で養殖が難しい魚類の培養肉の開発に力を入れる。魚の細胞から組成し、3Dプリント技術を活用して作る培養シーフード。ウナギ、レッドスナッパー(フエダイの一種)、サラサハタの3種類の魚の培養肉開発技術について、ナンヤン・ポリテクニック(国立技術高等専門学校)からライセンスを付与されている。
同社がこの3種類に注目したのは、需要が拡大する一方で供給量は減少しているためだ。養殖が難しく、絶滅の危機にあるような希少な魚の培養肉を開発することで、需給ギャップの解消を図るという。
「ウナギとサラサハタでは細胞の成長促進の最適化に成功し、現在は培養肉の生産工程を開発中だ。併せて栄養価、食感の向上も進めている」とペルシャドCEO。ウナギは日本から取り寄せた「アンギラジャポニカ」種、いわゆるニホンウナギの培養肉の開発に取り組んでいる。
「当社の培養肉は本物に近い形状。ウナギは焼いたときに皮がぱりっとした食感を楽しんでもらえるような商品作りを目指している。販売開始直後の価格は、既存のウナギと同水準に設定する。生産が商業ベースに乗れば4~5年でより低価格で提供できると見込んでいる」(ペルシャドCEO)
魚の切り身商品についてはアジアのほか、欧米でも発売に向けた準備を進める。今年は培養肉の切り身を使った料理などを試してもらうため、デモンストレーション・イベントや試食会を多く開催する予定だ。マグロの培養肉の開発も行いたい考え。
各種の培養食用魚は、24年末にはまず小規模なレストラン向けの試験出荷を始め、その後2~3年でキロ単位での量産を目指すという。【Celine Chen】

ウマミ・ミーツが開発した魚の切り身を使った料理(同社提供)