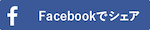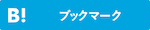【プロの眼】戦場のプロ 傭兵・高部正樹
最終回 傭兵人生に悔いなし
戦ってよかったこと
約19年に及ぶ私の戦場生活。つらかった事や苦しかった事を挙げれば、きりがありません。しかし、多くの得難い経験を積み、信頼できる仲間に巡り合えました。最終回は、長い戦場暮らしの中で良かった事、やりがいを感じた事などを書きたいと思います。

2009年、ボスニアのブコバルで戦没者慰霊式典に参加。フランス人、ドイツ人の戦友と久しぶりに再会した(筆者提供)
まず挙げるなら、人との出会いです。戦場という特殊な環境にいたせいか、普通の生活では絶対に接しないようなバックグラウンドの人間と多く知り合えました。みんな、ひと癖もふた癖もありますが、一度打ち解ければ命がけの戦場で頼りになる戦友となりました。戦闘は決して1人ではできません。いち早く人間関係を構築する事もまた、私に課せられた任務だと思っていました。
特に土地勘があり、われわれには得難い情報も持つ現地兵は、真っ先に距離を詰めたい存在でした。私が心掛けていたのは、彼らの言葉を使う事です。初めはそれが分からないので英語を使わざるを得ませんが、少しでも覚えた現地の言葉は直ちに使います。
いつまでも英語に固執しては溝が埋まりません。片言でも、現地の言葉を使うのが大事です。通じまいが笑われようが構いません。笑われたなら、むしろ壁を崩すチャンスと思っていました。仲良くなれた現地兵たちは、私にとって頼れる存在になってくれました。

ミャンマーで立ち寄った村。仲間の兵士や村人を相手にカレン語を勉強した(筆者提供)
中でも忘れられないのが、ミャンマー国内の民族であるカレンの軍で知り合ったモーター曹長です。私が前線拠点のワンカーキャンプに配属になった時、同じ部隊の先任下士官として最前線の防衛ラインで指揮をとっていました。
迫撃砲の雨の中、塹壕(ざんごう)を飛び出して応戦する勇猛さを見せる反面、小康状態になるとネズミやネコをぶら下げて来て「これ晩飯な」と、みんなを笑わせてリラックスさせようとする優しい男でもありました。普段は、私たちから「テイラー」とあだ名で呼ばれるほど裁縫が上手で、暇な時はよくミシンに向かって隊員の戦闘服の修繕などもしていました。
彼は面倒見も良かった。日本人の1人がパスポートを捨てて現地に住み着いて戦うと決めた時、身柄を預かってくれたのもモーターです。自分の家族の生活さえままならないのに難民キャンプの自分の家に住まわせ、衣食住の世話もしていました。その日本人は数年後に戦死しますが、彼がそこまで頑張れたのもモーターがいたからこそと思ったものです。
そんな彼の奥さんが突然キャンプを訪ねてきた時、自分の塹壕に貼り付けたヌード写真が見つかって平謝りしていた姿は忘れられません。その場にいたわれわれ日本人も、なぜか一緒になって奥さんに謝りました。
モーターはワンカー陥落直後に消息不明になってしまいましたが、われわれ日本人兵士にとって忘れ難い人物です。

ミャンマー・カレン軍のモーター曹長(左)、女性将校(中)と(筆者提供)
人生最高の戦友
仏人エリート兵
傑出した人物は現地人ばかりではありません。戦場には世界中から腕に覚えのある兵士が集りますが、中でもフランス人のガストン・ベッソンは特別な存在でした。フランス陸軍特殊部隊出身のエリートで、ミャンマーやボスニア・ヘルツェゴビナで共に戦いました。敵に1カ月以上も完全包囲されたミャンマーのワンカーキャンプではずっと隣にいましたが、日々悪化する状況を楽しんでいる印象さえ受けました。
ある朝食時、現地兵が「フレンチフライだ」と言ってつまようじのように細いフライドポテトを持ってくると「こんな貧相なものをフレンチと呼ぶな」と大声で突っ込み、すかさず「こんなものはリフュージーズフライ(難民ポテト)だ」と。笑いながら応酬するガストンと若いカレン兵のおかしさに、みんなが腹を抱えて笑いました。
その時は、最終防衛線を何度も突破されてキャンプが陥落寸前になる激戦の毎日でしたが、そんな中でもジョークが出るほど彼には余裕がありました。
20年ほど前、ガストンから「一緒に民間軍事会社(PMC)へ入ってイラクに行こう」と誘われた事もありました。「俺の背中を任せられるのはお前しかいない」と彼に言われた時は、本当にうれしかったものです。当時、既に名の通った存在だったガストンに兵士として最大級の信頼を示された事は、今も誇りに思っています。
彼はその後、ウクライナのマリウポリの戦いで名を馳せたアゾフ大隊(当時)のリクルーターとしても活躍します。2014年のアゾフ大隊の創設時、私も彼からオファーをもらいました。私は引退して数年たち「今更、出番でもないだろう」と断りましたが、誘いに乗っていたら昨年ニュースにもなった激戦のマリウポリで戦う事になっていたかもしれません。友人らには命拾いしたなと言われますが、兵士としては惜しい事をしたとも思っています。
その彼も22年に永眠しました。うわさではアルコール依存症が原因とのことですが、彼らしく豪快に逝った事と思います。私がボスニアに行けたのも、兵士として信頼が厚かった彼の豊かな人脈のおかげでした。今でも最高の戦友は誰かと聞かれると、このガストンの顔が真っ先に思い浮かびます。

フランス人のエリート兵士、ガストン・ベッソンと。2007年、タイのパタヤで再会(筆者提供)
若者が気遣い
引退を決意へ
私が引退したのは07年でした。当時いたミャンマーで険しいジャングルになった山岳地帯の行軍は、激しく体力を奪います。引退を決意したのは、行軍中に若い兵隊たちが私を気遣うそぶりを見せるようになったからでした。
もちろん、まだ現役でやりたい気持ちがなかったのではありません。しかし、この世界はスポーツのように自分が通用しなくなった事を確認するまでやる訳にはいきません。仲間の命をも危険にさらしてしまうからです。
当時まだ40歳代前半でしたが、長年にわたる無理やマラリアなどの風土病によって体は既にぼろぼろでした。日常生活ならともかく、過酷な戦場に要する体力は並大抵ではありません。若い時ならまだしも、毎日大きく削られる体力をわずかな休息で回復させるのは至難の業となっていました。
引退を決意した時、上官からインストラクターにならないかとオファーを受けました。「それならまだ大丈夫だろう」と。しかし、訓練した若い兵士を最前線に送り出し、自分は後方に残ってリスクを負わないという仕事はやりたくないので、断って帰国しました。

橋梁を破壊する作戦の終了後、部隊の戦友たちと(筆者提供)
誰かのために戦う
理想をやりきった
仕事も貯金もない状態での帰国を心配する友人もいました。しかし、生活に不自由するかなど、どうでもいい事でした。私には子供の頃から「他の誰かのために命をかけて戦う兵士になりたい」という理想がありました。理想に向けてやりきった自負もありました。
引退を決めた時、真っ先に思ったのは「この命でなすべき使命は終わった」ということです。自分はこのために生まれてきた、と信じる道をやりきった。その思いだけで、たとえホームレスになったところで笑って受け入れられる、そう思いました。
帰国した頃、知り合いに「お前は頑張ったつもりかもしれないが、結局、家族も財産も何も残ってない」と言われた事があります。からかったつもりかもしれませんが、それは私にとっては最大級の褒め言葉でした。
持てる時間もお金も気持ちも全てを余さず注ぎ込んで、幼い頃に信じた道を全力で生きてきたつもりでした。そんな私にとって「何も残っていない」という言葉は、私が余力を残さず生きてきた事の証だと思ったのです。
もちろん、辛かったり悲しくなったりするような記憶は頭にこびりついたままです。時には、散った戦友たちの無邪気な笑顔やフラッシュバックのように襲ってくる戦場の記憶に苦しめられることもあります。図らずも生き残ってしまった事に対する、戦友たちへの懺悔(ざんげ)の思いは消えることはないでしょう。
しかし、あんなに苦しい日々ばかりだったにもかかわらず、今となって思い出すのは彼らとの楽しい思い出や笑顔ばかりです。それはきっと自分の使命を果たした、やりきったという思いが心にあるからだと感じます。
そんな記憶や思いも含め、普通の生き方をしていたら絶対に得られなかった経験の全てが、私に唯一残った最も大切な財産だと思います。「自分の信じた道をやりきった」と自信を持って言える人生を生きることができ、本当によかったと今改めて思っています。

引退後、数年ぶりにカレン軍の第5旅団司令部を訪問。偶然、かつての戦友と再会した。「あどけない少年兵でしたが立派に成長していました」と高部氏(筆者提供)
日本人の慰霊
集うカレン人
01年、タイとミャンマーの国境にほど近い寺院の境内に、カレン族と共に戦って亡くなった3人の若き日本人兵士のための慰霊碑が建立されました。その「自由戦士之碑」という慰霊碑の除幕式に参加した時、私は驚くべき光景を目にしました。
除幕式の事は、建立に携わった日本人やカレン軍の上官・戦友たちなど身近な軍関係者にしか告げていませんでした。それが、どこから聞きつけたのか多くのカレン族の村人が駆けつけたのです。苦しい生活にあえぐ中、車で丸1日かかる難民キャンプからわざわざ来てくれた人もいました。
「みんな彼らに感謝しているんだよ。遠く日本からわれわれのために駆け付けて戦い、命を捧げてくれた日本人がいた事を。カレン人は、それを決して忘れない」。当時、上官だったアイザック大佐が、そう静かに口にしたのを今も忘れません。
欧米人の兵士たちに戦う理由を聞くと、ほとんどが「フリーダム(自由)のため」と言います。しかし、日本人は違います。誰もが「義のため」と口をそろえました。日本人が戦うのは、立派な主義主張のためではなく「今、目の前で苦しむ人々を何とかしたい」という、その一心だったのです。除幕式に集まった大勢のカレンの人々の姿を目にしたとき「誰に語らずとも、われわれの思いは通じていたのだな」と思いました。
「あの苦しかった日々も無駄じゃなかったな」
そのとき目に浮かんだ3人の面影に、そう語りかけていました。われわれの戦いは無駄ではなかった、それだけで十分でした。目に見えるものは何一つ残せませんでしたが、その思いだけで20年近くに及んだ私の戦いは十分に報われたのです。
1年にわたった連載も、今回で終わりを迎えることになりました。連載を始めた頃は、これまで書いた媒体とは読者層も全く違い、受け入れてもらえる自信はありませんでしたが、こうして1年間読んでくださり深く感謝を申し上げます。本当にありがとうございました。

慰霊碑の除幕式では日本から神主を呼んだ(筆者提供)