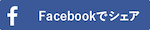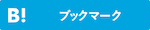【プロの眼】戦場のプロ 傭兵・高部正樹
第11回 悲劇は必ず起きる
戦場暮らしの現実
当然のことではありますが、戦地に何年もいれば目を覆いたくなるような悲劇的な場面に遭遇します。非戦闘員である市民が敵からの攻撃への盾にされたり、悪意ある味方に撃たれたり、幼い少年兵が亡くなったり、トラウマ(心的外傷)になるような場面をいくつも経験しました。こうしたことにも日常的に向き合うのが、戦場の現実なのです。

アフガニスタンで出会った10~14歳の少年兵たち。「本文で紹介する部隊ではありませんが、同じ年頃の少年たちが亡くなりました」と高部氏(筆者提供)
今も私の心に最も強く残るのは、アフガニスタンで出会った少年兵たちです。
私がいた当時の1980年代後半、現地の武装勢力であるムジャヒディン(イスラム戦士)の中に少年たちが混ざっていました。ほんの小学生か中学生くらいのまだ子供で、そんな少年が銃を持って闊歩(かっぽ)するのです。しかし、見た目は一人前でも顔にまだまだ幼さも残る年頃。彼らにとっては外国人が珍しいようで、私の周りによく集まってきました。いつの間にかそれがグループ化し、私のチームみたいなものができました。
ある日、少年らが実戦に出られるように訓練をしてほしいと上官に頼まれました。まだまだ難しいところですが、思案の末に「2カ月は欲しい」と告げると、いったんは了承してもらえました。ところが、それからひと月もたたないうちに「お前たちも前線に出て欲しい」と命じられたのです。近く大きな作戦を計画しており、その人手が足りないからだと。
もちろん、最初は断ります。訓練さえも中途半端にしかできていない少年たちを最前線に出すわけにはいきません。しかし、要請を何度も何度も繰り返されるうちに周囲の空気がだんだん変わっていきます。私が前線行きをかたくなに拒む姿に対し、不信や反感の目が向けられていることをはっきり感じました。
それに加え、自分が外国人という引け目も私にはあります。「臆病者に見られたくない」「日本人が腰抜けとは思われたくない」といった、個人的な気持ちが徐々に頭をもたげてきたことは否定できません。そして何より、当の少年たちが最前線行きを強く希望したのです。
私はその少年たちの気持ちを、自分の肩にのしかかる派遣要請へのプレッシャーから逃れる言い訳にしてしまったのかもしれません。「本人たちが行くというのなら・・・・」と。そしてついに、彼らの最前線行きを了承してしまったのです。この決断は、私にとって人生最大の痛恨の出来事として記憶されることになります。
8歳から15歳
前線に送り出す
「無理をする必要はない」
「絶対に指揮官を見失うな」
「1人で行動するな」
下は8歳から上は15歳の総勢13人。最前線に赴く彼らに、いろいろな注意を与えます。しかし、みんな年端もいかない子供たちです。最前線に着くと案の定、1人が前に、ある者は右へ、そして別の者が左にと、少年兵はすぐに散り散りになります。大人の兵士でも極限の精神状態に陥ってしまうのが最前線だというのに、初めて実戦に出る少年たちに落ち着いていけというのが、どだい無理な話なのです。そのうち、みんな私の視界からいなくなってしまいました。

空爆を受けた直後、もうもうと土煙が上がる。アフガンでは、このような前線に少年兵たちが投入された(筆者提供)
その日の夕方近くに戦闘が終わり、私は1人で最前線のやや後方にある拠点に戻りました。少年たちは誰も帰っていませんでした。そのまま拠点の前で待っていると、1人、2人とぽつぽつと帰ってきます。食事もとらず深夜まで待ちましたが、肩を落として打ちひしがれたような姿で帰ってきたのが全部で8人。5人はついに帰ってきませんでした。
前線の拠点は近辺の山中にいくつもあるので、どこか他の場所にたどり着いているんじゃないか。一筋の望みをかけて司令官が無線で問い合わせてくれましたが、彼らの姿はどこにもありませんでした。
その夜、私は後悔と自責の念にさいなまれて一睡もできませんでした。「なぜ、少年たちの最前線行きを最後まで反対できなかったのか」。そのことばかりが頭の中で渦を巻きます。仲のよいムジャヒディンたちは「お前がどんなに反対したところで結局、彼らは送られた。お前の責任ではない」と慰めてくれますが、後悔と自責の念は両肩に重くのしかかったままです。
後日、戦死した少年たちの遺体は回収されて葬られたようです。しかし、別の拠点に収容されて、そのまま後方に送られ埋葬されたので私は彼らの遺体と面会すらできず、結局どこに葬られたのかさえ分かりませんでした。
部下もう持たない
最大の痛恨と後悔
生き残った少年たちは、1人を除いて精神的ショックで落ち込んでいたので翌日には後方に戻されました。唯一残った血気盛んな15歳の少年だけは、われわれと共に最前線で戦闘を続けました。聞くところによると、その少年は敵の攻撃により家族を殺され、親類と難民キャンプで過ごしていたそうです。復讐(ふくしゅう)の念に燃えた彼は、ムジャヒディンとして戦うことを志願しました。
私はというと、数日間にわたる戦闘が終了して所属部隊の拠点に帰りました。しかし、生き残った少年たちとは、まともに顔を合わせることができませんでした。申し訳ない気持ちだけではありません。彼らに会うと、死んでいった少年たちの顔がダブって見えてしまうのです。

お菓子の箱を持ってはにかむアフガンの少年兵(筆者提供)
このことがあってから引退までの十数年間、私は部下を持つことを拒否し続け、あくまで一兵卒として戦場に立ち続ける道を選びます。「あんなつらい思いをするくらいなら部下などもう持ちたくない。俺に任せないでくれ」。そんな思いでした。
一方で、最前線に立つ将校というのは大したものだとも思いました。大勢の部下を持ち、そして常にそのうちの何人かを失うのです。私の戦友の1人は「部下を数字として見ることができなければ、将校は務まらないよ」と言っていました。「今日は誰が死んだ」ではなく「今日は何人死んだ」と考えられる人間でなければ、戦場での指揮官は務まらないと。正にその通りだと思いました。
私のキャリアの中でも比較的早い段階で起きたこの事件は、最大の痛恨と後悔、そして教訓をもたらし、私が戦場生活を引退するまで影響を及ぼします。引退しようとした時、インストラクター(教官)の仕事をオファーされましたが、それも断りました。
手塩にかけて訓練した若い兵隊を最前線に送り込み、そして何人かは確実に死ぬでしょう。その間、自分は彼らと同じリスクを背負うこともなく安全な後方で過ごす。そんな仕事はしたくないと思いました。そうした決断にも、少年兵の件が影響したのは否めません。今でも、後悔してもしきれないほどの出来事でした。
「故意に違いない」
味方の射撃で死亡
戦場で脅威となるのは敵兵だけではありません。こんな出来事もありました。
ボスニア・ヘルツェゴビナの南部の町で戦闘中、われわれは建物や家屋に分散して潜んで戦いました。その時、味方のカナダ人が潜む建物の2階の部屋で爆発が起こります。そのカナダ人は死亡。敵の砲弾を受けたのだろうと初めは思いました。
しかし、爆発の近くにいた部隊の兵士の何人かが疑問を口にします。カナダ人を殺した砲弾は、明らかに味方がいるはずの後方から飛んできたと言うのです。疑問というよりも確信がある口調でした。着弾点やその先にも味方しかいませんでした。そこで、その時の味方の配置を確認し直してみると、ある疑惑が浮上してきたのです。

ボスニア・ヘルツェゴビナの市街戦で、カナダ人の副隊長を殺害した物と同型の携行式ロケット弾「RPG7」(筆者提供)
亡くなったカナダ人は、われわれの部隊の副隊長です。われわれの部隊はあまり優遇されず、意見や要望は相当強硬に主張しないと通りません。そのため、交渉や折衝では時に外部との衝突を引き起こしていました。そういった交渉を一手に引き受けていたのが、この副隊長です。そして、イギリス人を主体とする教官チームに所属するAという隊員と険悪な関係になっていたのです。それは誰もが知るところでした。
副隊長を殺傷した砲弾が飛来してきた方向には、その教官チームがいたのです。通常、教官チームは前線に出ないのに、その時はなぜか隊員Aを含めて最前線に来ていたのです。
われわれは戦闘が落ち着いて後方に戻ると、一足先に後方の基地に帰っていた教官チームに怒鳴り込みました。「Aが殺したに違いない!」と。しかし、教官チームの隊長は「Aは副隊長を敵と誤認して射撃してしまったと言い、上級部隊の事情聴取にもそう応じている」と、かばいます。しかも、あろうことかAは帰って来るとすぐに休暇を取ってボスニアを離れた上、そのまま遠くの他部隊へと転出したというのです。

戦闘があって荒れ果てたボスニアの集落。市街戦は市民生活にも影響を及ぼす(筆者提供)
誤射は珍しくない
不問にされる事件
「Aはどこに行った」と食い下がるも、その隊長は「敵だと思って誤射してしまうのは、珍しい事でもないのは分かるだろう。君たちが騒いだところで、どうなるものでもない」と涼しい顔で言い放ったのです。
確かに、最前線での誤射は度々あります。間違って味方を撃ってしまったと言い張られたら、故意を証明するのは至難の業です。しかも正規兵ならともかく、われわれのような外国人の兵士同士のトラブルを真剣に裁こうという意志は、上官たちにはありませんでした。
こうしてAの行方は分からず、われわれは怒りの気持ちをぶつける場所もなく、うやむやのうちに事件は葬り去られたのです。実に後味の悪い事件でした。上官が言うように、誤射は珍しい事ではありませんが、決して不問でいい訳でもありません。ただ、この時の敵と味方が複雑に交錯する市街地の戦場では、残念ながら一介の外国人兵士に過ぎないわれわれが故意を証明することも困難でした。
その後、われわれと教官チームの仲はさらに険悪になりました。さすがに、一触即発のような状況になってくると上級部隊も対応に乗り出します。結局は教官チームが違う基地に移動となり、われわれの気持ちは不完全燃焼のまま決着せざるを得ませんでした。
この事件を通して分かるのは、アウトローの集まりだと思われている傭兵部隊でも大切なのは「人の和」なのです。いえ、傭兵部隊だからこそ、それが大切と言えるでしょう。
われわれは互いに武器を手にしているだけでなく、最前線で戦った経験も持ち合わせています。つまり、人に向けてトリガーを引く心のハードルは、一般の人が思う以上にかなり低いということです。
「あいつが気に入らない」などと不満がくすぶり続けると、ある日後ろからズドン、ということが起こり得る。注意しなければならないのは敵だけではない。それも1つの戦場での真実なのです。

ボスニアで高部氏が所属したチーム。右から5人目が、味方の射撃で死亡したカナダ人の副隊長(筆者提供)