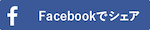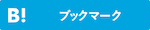【プロの眼】戦場のプロ 傭兵・高部正樹
第3回 戦場超える過酷さ?
収支赤字のお金事情
前回までは、1980年代後半にソビエト連邦と紛争中だったアフガニスタンに渡り、実戦に生まれて初めて参加した経緯を語りました。今回からは傭兵に関するさまざまなテーマを紹介します。まずは、傭兵がもらえる報酬や他の収入、懐事情といった「お金」にまつわるエピソード。そして、過酷さや危険の中で求める「やりがい」についてです。

帰国時は警備会社で内勤のアルバイト。夜は飲食店でも働いた(筆者提供)
まず、私が傭兵として世界各地で得てきた報酬について。初めてもらったアフガニスタンの報酬の受け渡しは、まるで山賊のようでした。戦闘後に数人単位でパキスタンに帰る際、指揮官クラスの人が大きなバッグに手を突っ込み、わしづかみにした札束を順番に手渡すのです。いちいち数えもしません。
一見、すごい量の札束で大金のようですが、現地通貨のアフガニは日本円ならわずか8,000円足らず。1カ月いようが2カ月いようが関係なく、金額はいつも同じひとつかみ。見事な丼勘定です。
現金での支給は助かりますが、当時のパキスタンではアフガニの両替は嫌がられました。しかし、外国人の私がアフガン国内でお金を使う機会はないし、日本に持ち帰っても役に立ちません。そこでいっそ、仲間に配ってしまうのが常でした。
後日談もあります。十数年後、東京の催しで古銭や世界のお金を扱うブースをのぞいた際、かつて支給されたのと同じアフガニ紙幣が並んでいたのです。ほんの数枚の紙幣に数千円の値が付いていて、本当に驚きました。
一方、90年に参加したミャンマーのカレン軍(反政府軍)は、例外なく全員無給でした。ただ、そこに集う外国人兵士は、貧しい少数民族から報酬を得ようとは誰も思っていませんので、無報酬でも問題ありませんでした。
94年のボスニアは、名前・認識番号・金額などが書かれた紙を受け取り、銀行で換金するシステム。指定銀行に設けた口座に振り込まれるのですが、われわれ外国人は必ず全額引き出しました。傭兵のほとんどは世界各地を転戦してきた猛者たちで、戦時中の国の銀行など全く信用していませんでした。

アフガン参加時、報酬を渡してくれた長老(右、筆者提供)
窓口で必ず聞かれたのが、クロアチア・ディナールとドイツ・マルクのどちらで欲しいか(私はクロアチア勢力に参加)。実に悩ましい問題で、当時の欧州最強の通貨だったマルクで欲しいのが本音ですが、駐留はボスニアの片田舎でマルクの使い勝手はよくありません。
逆にディナールは普通に使えますが、通貨として弱い上に紛争国はいつどうなるか分かりません。みんな悩んだ末、近く出国予定がある時はマルク、そうでない時はディナールでもらうようにしていました。
通貨変更でパニック
報酬が全て紙くずに
94年春、懸念は現実になりました。クロアチア政府が通貨変更をいきなり決定。ディナールは5月末までに「クーナ」に両替しないと使えなくなるといい、まさに寝耳に水です。部隊のほとんどは、報酬全額をディナールの現金で持っていました。運の悪いことに、両替する間もなく命令が下り、最前線に配置されてしまいます。しかも、いつもなら2週間もすれば後方にいったん戻れるはずが、こんな時に限ってなかなか戻れません。
月末が近づき、プチパニックを起こしたわれわれは車を何台か用意し、非番の仲間に全てのディナールを預けて方々に走らせます。しかし、前線近くに銀行などありませんし、あまり遠く離れる訳にもいきません。数日で紙切れになる紙幣を両替してくれる奇特な市民も皆無でした。
そしてタイムリミットの夜。日付が変わった瞬間、紙くずとなったディナールの紙吹雪が宙を舞いました。手にしたキャッシュが紙切れになる。こんな経験は二度とないでしょう。貴重な思い出です。
ちなみに、肝心の報酬額は180万ディナールほど。桁の多さに「おい、これで俺も夢のミリオネア(億万長者)だぜ」とふざけるのが部隊の定番でしたが、日本円では3万円弱。レストランでミックスグリルを頼んだら35万ディナール支払う。そういう金額でした。
先進国の出身者には「はした金」ですが、それまで東欧圏に属した旧ユーゴでは普通だったようです。私の階級は軍曹(報酬を決める便宜上の階級で命令権なし)でしたが、階級に応じた正当な額だと聞いています。
なお、両替レートは1,000ディナールで1クーナ。翌月から報酬は1,800クーナほどになり、つかの間のミリオネア気分すら味わえなくなりました。そんなわずかな報酬も経費の足しか酒代になり、いつの間にかなくなるのが常でした。

ボスニアの仲間と。わずかな報酬は仲間と飲むのが正しい使い道。「それしかないというのもありましたが、結束を深めることが大切でした」(筆者提供)
「傭兵は高給のはず」
実はスポンサー次第
「傭兵は高給を得ているはず」と思う人は多いと思います。私もそういうイメージでした。傭兵を志したのは80年代後半。直後に冷戦が終結し、世界は民族紛争や宗教紛争の時代に突入します。主な戦場は発展途上国で、スポンサーは貧乏な国や組織ばかり。兵隊は欲しがりますが、ない袖は振れないのです。
アフリカで戦う元英国軍の特殊部隊隊員と知り合った時、エリートの彼でさえ報酬は月300米ドルだと嘆いていました。当時、某国のミリタリー誌がわれわれを「LOW PAY HIGH RISK」と評したのは的を射た表現です。
ところが、2000年代には一変します。03年に始まったイラク戦争をきっかけに、民間軍事会社が台頭。金に糸目をつけない米国をバックに高給で雇います。ボスニアでは月3万円弱だった同僚が、イラクでは日給5~10万円に。私も戦友に勧誘され、その時のオファーは日給約7万円でした。傭兵の報酬とは時代や場所、つまりスポンサー次第なのです。
一方、イラク戦争は確かに相場を上げましたが、あくまで局所的なバブルでした。近年は、米国がスポンサーで高収入を望めたアフガニスタン戦争も終結。残るアジアやアフリカは依然「LOW PAY HIGH RISK」で、傭兵には冬の時代の再来かと思えました。しかし、今年に入りウクライナで戦争が発生。米国の積極支援で、ウクライナ側の傭兵はそれなりの報酬を得ているようです。
また、傭兵の優劣を報酬額で語る人がいますが、正しくはありません。少なくとも時代と場所が同じでなければ比較する意味がないからです。

収支はいつも赤字
バイトに励む日々

昼間に警備会社で仕事した後は、東京の新宿・歌舞伎町の飲食店でバイト。「夕方からラストまで毎日勤務、終電で帰宅していました」(筆者提供)
われわれの時代、収支は赤字が当然。スポンサーも合流後は面倒を見てくれますが、現地までの渡航費や個人装備品は自腹です。特に航空機代が負担でした。1回の渡航でアフガニスタンは少なくとも約25万、ミャンマーも10万円は必要でした。14年にウクライナのアゾフ大隊からオファーが来た時も「キーウまでの往復は自腹で」と告げられました。
その頃は、とにかく必死でした。赤字の穴を埋めるため、帰国後はアルバイトに励みます。昼間は警備会社、次は深夜まで飲食店、休日は交通量調査員。長野の白骨温泉に住み込みで働いていたこともあります。1日でも早く戦場に戻るため、働き詰めでした。生活費も切り詰めます。食事は毎日キャベツと納豆ご飯。真冬も風呂を沸かさず、震えながら冷水を頭からかぶっていました。

タイでNGO職員という名目でビザを取得。「全く何もしない訳にもいかないので時折、日本語を教えていました」(筆者提供)
90年代半ばになると、単行本や雑誌連載の執筆を依頼されるようになり、わざわざ帰国してアルバイトする必要はなくなりました。当時、ミャンマーのカレン軍が主戦場だった私は拠点をタイに移しました。それまで、観光ビザでタイに入国してはビザが切れる前に日本か第三国に出国することを繰り返していましたが、今度はNGO職員というアンダーカバー(建て前)で非永住ビザと労働許可証を取得。長期滞在が可能になりました。
他の外国人兵士も、会社を設立したり現地の女性と結婚したり、あらゆる手を使い収入源と長期滞在ビザの獲得に動きます。できない者はいったん帰国するしかありません。世渡り能力や人脈作りも、当時の傭兵には必要なスキルだったのです。
お金よりもやりがい
「何もない」誇りに
こうした苦労を重ねていましたが、不平不満を漏らす者は誰一人としていません。むしろ、そういう生活をみんなが楽しんでいました。それは、お金よりも自分なりのやりがいを誰もが持っていたからだと思います。
例えば、欧米の兵士に戦う理由を尋ねると「アドベンチャー」とか「フリーダム」と口にします。日本人は「正義」が圧倒的に多い。あまり詳しく聞く事はありませんが、それぞれが色々なやりがいを胸に秘めていたと思います。そうでなければ報酬も少ないのに、こんな危険で苦しい事は続けられません。
私のやりがいは、子供の頃からの夢を実現しているという思いでした。自分ではなく他の誰かのため、何かのために戦う軍人になりたい。報酬や見返りがなくとも、そういう事を平然とできる男になりたい。それを実現できていると思えば、どんなに困窮しようと男としての幸せを感じられたのです。「あの頃の自分に見られて、恥ずかしい生き方をしていないか」、それが長い傭兵生活を支えてくれたモチベーションでした。
そんな生活のせいか、2007年に引退して帰国した時には全財産は10万円にも満たず、家族も仕事も住む場所さえもありませんでした。他の人には「偉そうに言うけど、お前には何も残ってないよね」とよく言われたものです。確かに普通の日本人から見たら単なるバカでしかないと思います。
しかし、私には「何も残ってない」と言われる事はむしろ褒め言葉でした。持てる力の全てを余さず注ぎ込み、自分で決めた道を歩んできた。その証拠だと思えたからです。
戦場では、誰もが死に物狂いで故郷のために戦っていました。そうした中で、自分の将来や取り分、余力、逃げ道をしっかり用意しておくという覚悟のなさや、やり方は納得できませんでした。私にとっては「何も残っていない」ことが、この上ない誇りだったのです。

ボスニアの仲間と。「お金がないので、休暇中の昼間は近くの川で泳ぐのがポピュラーな過ごし方でした」(筆者提供)
なお、私が監修に協力する単行本新刊『日本人傭兵の危険でおかしい戦場暮らし 戦地に蔓延(はびこ)る戦慄の修羅場編』(竹書房、にしかわたく・著、5月5日発行)では、前回や今回のお話に関連するエピソードも登場します。よろしければ併せてご覧ください。