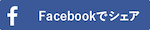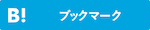【プロの眼】インド食文化のプロ 小林真樹
第4回 日本のインド料理店(上)
間口広げたネパール人
現代日本のインド料理シーンを概観する時、その流れを特徴づける二つのファクターが浮かんできます。一つは躍進するネパール人経営者によるインド料理店、もう一つはIT系インド人経営者による南インド料理店です。これらを見ていくことで日本のインド料理店の特徴を把握でき、そこで食べる料理の味わいも一層深く感じられるかもしれません。

1970年代に創業した「モティ」。重厚感ある内装が年代を物語る(筆者提供、以下全て同)
まずは、躍進するネパール人経営の店からご説明しましょう。日本におけるインド料理店の嚆矢(こうし)とされるのが、1949年の創業で現在も銀座で営業中のナイルレストラン。その後、60年代から70年代にかけてアショカやタージ、モティといった店が銀座や赤坂、六本木などに開業していきます。
その立地からも分かる通り、初期のインド料理店はかなりの高級路線を打ち出していました。料理はカシューナッツや生クリームを多用したリッチなカレーを、タンドールと呼ばれる窯で焼き上げた大きなナンで食べさせるスタイル。

典型的なナンとカレーのランチセット。こってりクリーミーなバターチキンはインド料理店の人気メニュー

あんこ入りやチョコレート入りなど、インド本国では見掛けない創作ナンが多いのもネパール人経営店の特徴の一つ
大半の店で、このタンドールは店内や店外の客から見えるよう強化ガラス越しに設けられていました。ナンを焼くという専門技術が大きなセールスポイントでもあったからです。
内装も凝っていて床や壁に大理石を多用。天井からはシャンデリアが吊るされ、インドから輸入された高価な調度品で一面が装飾されていました。
当初は東京中心部に点在していたインド料理店が、徐々に地方都市でも見られるようになのが80年代あたりから。それとともに調理スタッフも多く来日するようになりました。
この調理スタッフの中に、インド人だけではなくネパール人調理師が多く含まれていたことが、その後の国内インド料理店の興隆を見ていく上で重要になります。
調理師から独立
ネパール人の店

東京・江東区森下にある「ギータ」の厨房(ちゅうぼう)。典型的なネパール人オーナーの店
ネパールはインド北部と国境を接した隣国で、相互の往来にビザが不要なことから現在でも多くのネパール人がインドに働きに出ています。特定の技能を持たない季節労働者が多い一方、インド軍に軍人として勤務するネパール人も約5万人いるといわれます。
もちろん、ホテルや食堂の厨房(ちゅうぼう)で働くネパール人も多く、インド人に比べて真面目で従順なネパール人は雇用主から重宝され、重要なポジションを任されるケースも多々あります。
こうしたことから、日本で事業展開するインド料理店オーナーからも信頼を得て、徐々に招聘(しょうへい)され来日するようになっていったのです。
80~90年代にかけて増え始めたインド料理店の厨房で働いていたネパール人調理師たちが資金やビザ(査証)を整え、やがて独立し出すのが2000年代に入ってからです。
自らが経営者となる場合、自己資金で店舗と事務所を準備した上で経営ビザを取得することが必要となります。中には、真面目にコツコツ働いて永住権を取得する人もいます。
日本では永住権の取得条件の一つに「原則10年以上日本に在留していること」がありますが、80~90年代から働きはじめたネパール人調理師にとって、ちょうどそれに差し掛かるのが2000年代なのです。
もちろん、経営ビザにしろ永住権にしろ、厳しい審査を経て得られるもので、申請すれば誰でももらえるものではありません。
さて、独立したネパール人が自らの店で提供するのは、当然ながら長年働いた高級インド料理店を踏襲した味になります。
とはいえ、同じ境遇のネパール人が続々と参入する中、ライバル店との熾烈(しれつ)な競争をサバイブするためには対抗策を講じなければなりません。必然的に低価格化していきます。
従来、高級なイメージで売っていたインド料理を、特にランチ時は安くすることで集客を図りました。しかし、結局のところ単なる低価格化による競争は質の低下を招き、当初こそ確保できた客も次第に離れていくことになります。
子供連れの家族客に
ファミレス風セット

鮮やかな色味のコントラストが目を引くギータの2色カレーセット、ナン付き。ナンと辛さが選べるカレーの組み合わせも今やすっかり定着した
一方、そうではないところで勝負しようとするネパール人経営者も台頭してきました。
ある程度価格は抑えつつも品質は担保する。あるいは、子供連れのファミリー層向けにファミリーレストラン風のセットメニューやドリンクバーを取り入れたり、ガパオやトムヤムクンといったタイ料理、ベトナム料理などもメニュー化したり。リーズナブルな価格でライトなアジアン料理全般を提供することで間口を広げています。
このような路線で順調に成長した代表的な店として、東京を拠点とするディップマハルや神奈川を中心に支店を増やすハッピーなどがあります。
一定の顧客ニーズと経営モデルを把握したネパール人経営者はそのノウハウを蓄積し、やがて大型ショッピングモールのフードコートや駅ビルといったテナントへと果敢に進出していくのです。
このようなネパール人経営者の中には、インド料理店のコック上がりだけではなく、もともと留学生として来日した人たちも少なからずいます。
彼らは学校を出た後、居抜きで店舗を取得して営業を始めます。学生時代に居酒屋などでアルバイトをした人が多く、必然的にそのノウハウを自らの店に応用していきます。
従ってこうした店では枝豆やら焼き魚やら、妙に日本の居酒屋風のメニューが充実していたりもします。日暮れ頃、郊外の駅前などにあるこうしたインド料理店を、仕事帰りらしいサラリーマンが飲み屋代わりに使っている光景も珍しくなくなりました。
富裕層の料理を
大衆化した功績

東京・江東区三好の「サッカール」はホッピーなど居酒屋風メニューが充実。インド風にアレンジされたメンチカツカレーもおいしい
日本の成功店や繁盛店の功績は、かつて一部の富裕層のものだったインド料理を、より広く大衆化させた点にあります。
こうした店では、今やおなじみとなったバターチキンやチーズナンといった定番の他、ピザナンだったり明太子入りのナンだったりと、日本人の好みに合わせた新しいインド料理メニューが日々開発されています。
インド本国のものからは随分と乖離(かいり)してはいますが、そもそも世界中の外食店の料理は同じように発展してきた経緯があり、むしろこのダイナミックな変化にこそ「外食インド料理の本質」があるように思います。
こうしたインド料理をオリジナルに忠実であろうとするインド人オーナーではなく、中間的な立場ともいえるネパール人オーナーが担っているのも象徴的かもしれません。
食には時代によるトレンドが色濃く反映します。日本で食べられているインド料理もまたしかり。
「カレーにナン」というおなじみの組み合わせは、一見するとインド伝来で永久不変のように思えますが、その実、提供する側はあの手この手で市場の潜在ニーズを引き出そうと新規メニューやサービスの開発にまい進し、日々進化あるいは深化しているのです。
日本人の好みを知悉(ちしつ)したネパール人によって進化する日本生まれのインド料理、その醍醐味(だいごみ)を楽しみたいものです。
現代日本のインド料理店を形作るもう一つの流れ、IT系インド人経営者による南インド料理店については、次回詳しくご紹介したいと思います。