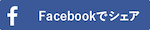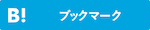【アジア取材ノート】
安く早くおいしく届く
インド低温物流の新時代
スマートフォンの注文一つで、新鮮な魚の切り身が冷蔵されたまま届く。インドで独自の低温物流(コールドチェーン)を手掛ける新興企業が台頭してきた。食肉や水産物など生鮮品を自社加工し、クーラーボックスを積んだ自前のバイクで配送する。コロナ禍による宅配利用の増加も追い風だ。インドで変わりつつある、新たな食品物流の姿を伝える。(取材=NNAインド 天野友紀子)

バイクで生鮮品を輸送するリシャスの配達員=インド・グルガオン(NNA撮影)

クーラーボックスは断熱材を何枚も重ねた構造で保冷剤を入れて運ぶ=同(NNA撮影)
スマートフォンアプリ「リシャス」で白身魚の切り身を注文すると、1時間ほどでバイク便がやってくる。鮮魚は自社工場でさばいて真空パック。商品によっては味付けもされている。
配送に走るバイクは約1,200台。特殊な断熱材を何層も重ねた特注のクーラーボックスを使い、保冷剤を入れて運ぶことで低温を維持する。
2015年設立のディライトフル・グルメ社は、「リシャス」ブランドで食肉や水産物のインターネット販売を展開する。デリー首都圏などインドの主要7都市・地域で60万人余りが利用している(今年6月末時点)。
自社でコールドチェーンを整備。工場でパックした商品は計70カ所ある中継用の配送センターに運び込み、そこから近隣の消費者へと届ける。本拠とする南部ベンガルールや北部グルガオンなど計5カ所の加工工場は、食品安全の国際規格「FSSC22000」を取得済みだ。
創業者のアバイ・ハンジュナ氏によると、インドの食肉や水産物のほとんどが衛生的懸念の残る屋外の市場で流通。スーパーが扱う品も化学物質や防腐剤が含まれている恐れがあり、消費者は不信感を拭えずにいるという。
「新鮮で質の高い肉や水産品にお金を払う消費者はいるのに、その選択肢がインドにはない」と考えたハンジュナ氏は、リシャスを立ち上げた。
物流のラストマイル
自前で一から構築
リシャスにとって一番の問題は物流の最終工程、消費者に届ける「ラストマイル」だった。「インドには温かい料理のためのラストマイルしかなかった。誰かがやるまで待つか、自分でやるかの二択しかなく、後者を選んだ」(ハンジュナ氏)
コールドチェーンの第1段階は、養鶏場など仕入れ先から加工工場まで。第2段階は、工場から配送センターまで。ラストマイルとなる第3段階は、配送センターから消費者の手元まで。第1~2段階は低温物流業者から冷蔵車を借りてまかない、ラストマイルは一から構築した。

注文した肉や魚は、生のまま真空パックにされた状態で届く=同(NNA撮影)
グルガオンのとある配送センターでは、15人の配送員が毎月約1万件の注文に対応する。1回の配送(90分~2時間)でこなす注文の数は、多いときで20件以上。専用に開発したシステムで最も効率の良い配送ルートを割り出している。
新型コロナウイルス感染症の流行を受けて、リシャスの成長は加速している。「消費者の意識は大きく変わった。安全性と品質は妥協できない要素となった」とハンジュナ氏。コロナ対策の全土封鎖でネット通販の利用者が拡大したことも追い風だ。
今年4~6月期の需要は、同1~3月期の4倍に膨れ上がった。1日当たりの配達件数はコロナ発生前に比べ2倍余り、平均注文額は30%とそれぞれ増加。ユーザー数もコロナ前の40万人から6月末までに62万8,000人と、1.5倍以上に増えた。
巨大保冷剤をトラック搭載
太陽光発電でコンテナ冷却
インド市場は価格に敏感で、コールドチェーンに対価を支払おうという荷主や消費者が極端に少ないというのが専門家の共通認識だ。
野村総合研究所(NRI)のインド法人、NRIインディアで物流部門を担当する羅俊明シニア・マネジャーは「お金がかかる低温輸送は『要らない』というのが99%の人の意識。そうではない1%はどこにいて、何に困っているのか。その需要をつかむことが重要」と指摘。先に紹介したリシャスは、この1%未満を狙った代表例と評する。
一方、お金を払っても良い品を求める中間所得層の拡大を背景に、輸送品質の向上に取り組む事業者も増加。「巨大な保冷剤を搭載した冷蔵トラック」や「ソーラーパネルを取り付けたコンテナ型の冷蔵倉庫」といったアイデアで、安価なコールドチェーンを手掛ける新興企業が登場している。
13年設立のサーマル・エナジー・サービス・ソリューションズ(テソル)は、保冷剤の進化版ともいえる「蓄冷バッテリー」を販売。特許製法で化学物質を配合した液体の入ったプラスチック容器で特定の温度を10時間以上維持でき、特にトラック向けの大型品は導入拡大が期待される。

テソルの蓄冷バッテリーを搭載した保冷車(左、同社提供)と内部(右、同)
従来型の保冷車(1トンのディーゼル車)の場合、リース料が月8万5,000ルピー(約12万円)ほどを要するのに対し、蓄冷バッテリー搭載車なら月6万ルピー前後で済む。米食品大手モンデリーズ・インターナショナルのインド法人や、「アムル」ブランドの乳製品で知られるグジャラート牛乳販売協同組合連盟などがテソルの保冷車を導入した。
インドの新興企業の情報収集を専門とする日系企業関係者は「インドの低温物流は保冷車が高価なことが課題の一つ。テソルは普通のトラックを改造し、価格を抑えている」と注目する。
太陽光の利用で運用費がほとんどかからない冷蔵倉庫を提案する企業もある。10年にインド工科大学カラグプール校出身者が設立したエコゼンだ。
屋根に太陽光パネルを取り付けたコンテナ型倉庫「エコフロスト」を15年から販売している。農家が収穫した野菜や果物、生花を冷蔵する用途で開発した。

屋上に太陽光パネルを配置したエコゼンの冷蔵倉庫(同社提供)
太陽光の電力で倉庫を室温4~10度に冷やすとともに、内部に張り巡らせた62枚の蓄冷板を冷却する仕組み。「太陽光がなくても、最大30時間は内部を10度以下に保てる」と同社。送電網につないで電力を得ることもできるという。
累計の設置台数は160台。農家が手軽に導入できるよう、収穫期の間だけリースすることも可能となっている。
前出の日系企業担当者は、2社の事業について「今ある資源で、いかに効率的にコールドチェーンを実現するかにフォーカスした、的を射たサービス」と評価。長期的にはインドだけでなく東南アジアやアフリカなど、「他の途上国でも需要が見込めるのでは」と期待を寄せている。
「業界は急成長の時代に入った」
印低温物流大手CEOインタビュー
1993年設立の地場コールドチェーン大手、スノーマン・ロジスティクス。スニル・ナイル最高経営責任者(CEO)は「食品安全の規制強化を追い風に、業界は急成長の時代に入った」と語る。インドのコールドチェーンの歴史と、今後の展望を聞いた。(聞き手=天野友紀子)

スノーマンのナイルCEO=インド・南部ベンガルール(NNA撮影)
――インドのコールドチェーンはいつから存在したのか。
農産物では40~50年前からある。農産物の冷蔵保存量ベースでは世界最大規模のコールドチェーンを持つ。手掛けるのは小規模業者でジャガイモが8割を占め、リンゴも多い。現代的な冷蔵倉庫や組織化は25年ほど前から、多国籍企業のインド進出を背景に発展した。外資の大手ファストフードなどがコールドチェーンを探し、結果として当社やラダクリシュナ・フードランドといった専門企業が誕生した。
――小売業者も食品メーカーも価格重視でコールドチェーンを使わないと聞く。
指摘の通り、価格は大きな問題だ。食品は価格を決めてから開発に取り組むところがある。1個20ルピー(約28円)想定のジュースにコールドチェーンは使えない。
――政策の効果が及ばず、コールドチェーンが進化していないとの指摘がある。
政府は青果物に焦点を当て、内陸部や農村部に食品産業団地(フードパーク)を設けてコールドチェーンを整備しようとしてきた。だが、採算を取るには相当の規模がいる。内陸部や農村部には高いコストに見合うほどの物量がない。冷蔵トラックで運ぶことで値段が3倍になったトマトを誰が買うのか。野菜や果物は、購入から2日以内で消費するのがインド人の習慣だ。
――そのような市場で、会社をどう育てる。
政府による食品安全の規制強化を背景に需要は増加した。5~6年前までは多国籍企業だけが質の高いコールドチェーンを求めたが、インド企業にも広まっている。無数の小規模倉庫を組織化し、効率化しようとする動きも起きている。そうした中、当社が主力とする輸出向け海産物、乳製品、飲食チェーン向けなどの取り扱いによる売上高は、今後は年率20%で拡大すると予測している。業界はやっと、急速に成長する時代に突入したと実感している。

インド南部ベンガルールにあるスノーマンの本社兼倉庫(同社提供)