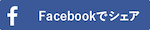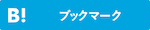「東西」の本から「亜州」を読み解く
アジアの本棚
『通信の世紀 情報技術と国家戦略の一五〇年史』
大野哲弥 著
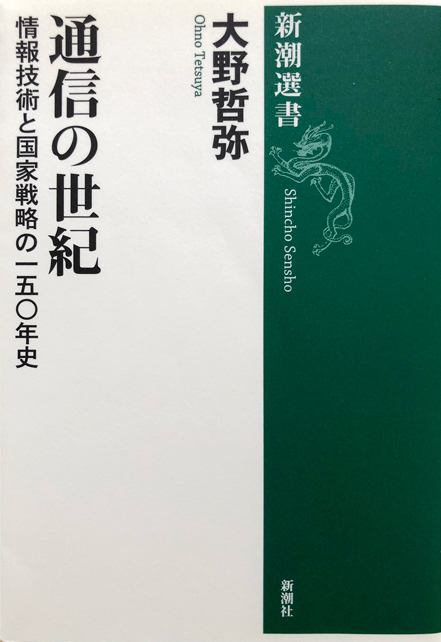
米中の対立は貿易から外交、科学技術、メディアまで広範囲に拡大しているが、通信もその一つだ。
ポンペオ米国務長官は8月上旬、中国企業による米国内での通信事業の制限を目指す新方針を発表した。中国で広く普及する「微信」(ウィーチャット)など中国製通信アプリの使用禁止やクラウド事業の制限などに加え、海底ケーブル通信網からも中国企業を排除するとしている。
主要国を結ぶ海底ケーブルは国際通信の最も重要なインフラの一つであり、これがなければインターネットも役に立たなくなる。現在では世界全体の海底ケーブルのうち3分の1を中国企業が敷設しているというが、敷設が始まった19世紀当時から外交的な武器としての色彩を帯びていた。
今回、紹介する大野哲弥著『通信の世紀 情報技術と国家戦略の一五〇年史』は、一般にはよく知られていない国際通信の技術革新とそれを巡る大国の戦略の歴史を、国際通信の専門家が詳述した労作。米中のし烈な攻防の背景理解にも役立つ。
日本で最初に海底ケーブルが陸揚げされたのは、約150年前の明治4(1871)年。長崎と上海を結ぶ通信回線だった。当時の海底ケーブルはデンマークの電信会社などが独占的に敷設しており、日本のような後発国には利用条件も厳しかった。
この年の暮れに訪米した岩倉具視の使節団が、翌明治5年の1月にサンフランシスコから無事到着を知らせる電報を打った。これが、日本が初めて受け取った国際電報だった。当時の太平洋にはまだ海底ケーブルがなかったことから、使節団の電報は米国から大西洋を抜けて欧州やアジア経由で3万キロを回り、前年に敷設されたばかりの上海のケーブルを通って長崎に着いたという。
日本も次第に独自のケーブル網を展開していくが、1930年代になると長短波による無線通信技術が発展、一時は無線通信がケーブルを凌駕した。戦後の衛星通信の時代を経て、伝送量が圧倒的に多い光ケーブルが登場すると主役は再び海底ケーブルに戻り、現在に至っている。
著者の筆は、日米開戦当時の宣戦布告電報の伝達遅れの問題から、米国当局による組織的盗聴を暴露したスノーデン事件にまで及ぶ。通信インフラを握る大国は、昔から他国の通信情報を盗聴、解析してきた。今、米国が「中国企業の製品を使うと中国政府に情報が漏えいする」と主張しているのも、自らの経験に裏打ちされていると理解できる。
著者が振り返るように「国際間の伝送路整備が、必ずしも国と国の相互理解や和平に寄与していない」のは事実だ。現在は海底ケーブルの敷設主体も、通信会社からグーグル、マイクロソフトなど大手IT企業に変わりつつある。通信インフラを巡る攻防は今後も主役を替えて続いてゆくはずだ。
『通信の世紀 情報技術と国家戦略の一五〇年史』
- 大野哲弥 著 新潮社
- 2018年11月発行 1,400円+税