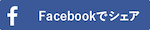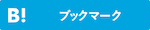【アジアの穴場】
フランス植民地時代の残照色濃く残る街
ターケーク(ラオス中南部)

ターケーク市内の祈念堂
東南アジア諸国連合(ASEAN)の中でも最貧国、日本からの直行便がなく最も遠い国、そして「何もない国」(旅行会社の宣伝文句)といろいろな形容詞で語られるラオス。だが、その各地にはかつての宗主国フランスの面影が色濃く残っている。中南部メコン川沿いのカムムアン県の県庁所在地ターケークもそうした地方都市の一つで、歴史と仏教の街である。
目抜き通りのクーウォラウォン通りを西に進むと、メコン川の手前のナンプ広場に建つ祈念堂がある。この祈念堂は1946年3月21日、ターケークで仏植民地軍とラオス人、ベトナム人による戦闘「ターケークの戦い」で犠牲となった人々を追悼する施設である。
この時の戦いで約3,000人が殺害され、その一部が遺棄されたという井戸が祈念堂にあり、花を手向け犠牲者を鎮魂するために手を合わせる市民の姿があった。
植民地時代の建物は今も現役
祈念堂の周囲に特に多く残されている仏植民地時代の建物は、その多くが現在も商店や住宅、商業施設などとして利用されている。
カフェやレストラン、そしてホテルは内部を改装されながらも外観は当時の面影を残しており、異国情緒豊かな街並みを形作っている。
祈念堂のはす向かいにある「インティラー・ホテル」は植民地時代の商家の趣を最大限残しながら改装されており、インテリアや家具なども当時をしのばせてくれる。1階のレストランではラオス料理とともにフランス料理も楽しめる。
仏植民地の雰囲気を漂わせる街であることからか、欧州からの白人観光客も多く、レンタル自転車で市内を巡りながら、店先で「ビア・ラオ」(ラオスを代表するビール)片手に「ラープ」(代表的ラオス料理で魚や肉をレモン汁、香草と炒めた料理)を食べる様子がよく目につく。
人々の生活に息づく仏教
中心部のメコン川沿いに建つ「Wat Na Bo(ナ・ボー寺院)」では7月16日、仏教の雨安居(雨期に若い出家僧が一定期間寺にこもって修行する)の行事が行われており、早朝から多くの市民が正装して僧に托鉢(たくはつ)するもち米、菓子、生花などを持ち寄っていた。
同寺院は境内に巨大な神木があり、お供え物を捧げる人々が後を絶たなかった。
裏手のメコン川に面した場所にはナーガ(蛇神)を模した入り口があり、対岸のタイ・ナコーンパノムは目と鼻の先である。
この川岸に沿って開かれるナイトマーケットでは各種麺類、焼き鳥、焼き魚などの地元料理を売る屋台が並び、タイの夜景を見ながら食事を楽しむことができる。ここでも主役は「ビア・ラオ」だ。
「何もない」とよく言われるラオスだが、地方都市には古き時代の歴史と文化が息づいており、熱心な仏教徒による祈りを中心とした生活の中でゆったりとした時間が流れている。それがラオスの魅力といえるだろう。(文・写真=PanAsiaNews 大塚智彦)

ナ・ボー寺院で托鉢を待つ人々