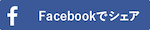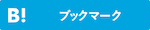【アジア取材ノート】
カレーをインドに逆輸出、日本企業の挑戦
甘くない市場、ベジタリアンの壁を乗り越えろ
インド
カレー発祥の地、インドで日本式のカレーを提供する日本企業の動きが相次いでいる。向こう3年以内の進出を見据えるのは、大手チェーン「カレーハウスCoCo壱番屋(ココイチ)」。一方、既に現地のレストランで日本式カレーの提供を始めたKUURAKU GROUP(千葉市)は、インド人客から上々の反応を得ている。大塚食品も元祖レトルトカレーの「ボンカレー」でインドに挑む。ただし、発祥はインドでも英国経由で日本に伝わったカレーはインドのものとは全くの別もの。人口13億人の有望市場である半面、国民の多数をベジタリアン(菜食主義者)が占めるなど文化的・宗教的な障壁も高い。各社の戦略を追った。(文=NNA東京編集部 須賀毅)

KUURAKU GROUPはインドでベジタリアン対応の日本カレーを提供している=ニューデリー(同社提供)
ココイチを運営する壱番屋(愛知県一宮市)は、1994年に初めての海外店舗を米国ハワイにオープンしたのを皮切りに、2018年6月末時点で中国や韓国、台湾、タイなどアジアを中心に10カ国・地域で計157店を展開している。その壱番屋の浜島俊哉社長が究極の目標として掲げるのが、「カレーの本場」であるインドへの進出だ。13億人の人口を抱え、日常的にカレーを食べる食文化を持つ同国を最大の有望市場とみている。向こう3年以内のインド進出を見据える。
日本カレーは全くの別料理
ただし、明治期に英国経由で伝わり、独自の進化を遂げてきた日本のカレーは、インドのものとは大きく異なり、「逆輸出」の壁は決して低くはない。例えば、日本のカレーは、小麦粉でとろみをつけたものが大半だが、インドでそうしたカレーはみられない。カレー商品の開発などを手掛けるカレー総合研究所(東京都渋谷区)の井上岳久代表は、「インドのカレーはスパイスの調合や香りを味わう料理。うま味やコクを特徴とする日本のカレーとは根本的に異なる」と指摘する。
日本式のカレーを提供する上で、最大の障壁と考えられるのが、インド国民の多数を占めるベジタリアンへの対応だ。人口の8割を占めるヒンズー教徒は、神聖な動物である牛の肉は食べない。鶏肉と羊肉(マトン)は食べてもよいとされるが、基本的には菜食が理想とされる。また、ヒンズー教徒に次いで多いイスラム教徒は、豚を食べることが禁じられている。
日本のカレーの味の特徴は、動物性エキスを使ったうまみだ。井上代表は、日本のカレーについて「牛肉や豚肉を使わないチキンカレーでも、ルウに牛肉エキスが使われている。純粋に鶏肉だけを使ったカレーというのはほとんどない」と説明する。動物性原料を使わずに、いかに日本式カレーのうまみやコクを再現するかが成功の鍵を握ると分析する。
実際、日本のカレーがインドで受け入れられそうか、NNAが独自に日本のレトルト式のカレーをインドに持ち込み、インド人による試食を試みたが、動物性エキスが含まれていることを理由に断られ続けた。非ベジタリアンであっても「豚肉と鶏肉など異なる種類の肉をひとつの料理で使うのはありえない」との断固拒絶の反応が印象的だった。そうした中、試食に唯一協力してくれたのが仕事でたびたび海外に出かけるという男性のプラシャント・コーリさん(36)。「個人的には好きな味。ただし、非ベジタリアン向けということを別にしても、多くのインド人が好む味とはいえないと思う。現に僕の家族はまったく興味を示さなかった」と話した。
壱番屋は、そうしたインド市場に合わせたカレー作りに向けて、まずは英国への進出を予定している。英国はかつてのインドの宗主国であり、インド系の住民も多く暮らす。ロンドンでインド人向けのカレーを提供するためのノウハウを蓄積することで、インド進出の足掛かりとする戦略だ。ロンドンには年内に出店予定という。
鍵は「スパイシー」「オイリー」「クランチ―」
既にインドで日本式カレーの提供を始め、好評を得ている日本企業もある。同国で日本レストランを展開するKUURAKU GROUPは今年1月、首都ニューデリーのインディラ・ガンジー国際空港(IGIA)近くの商業施設内に開業した「TOKYO TABLE」で日本式カレーの提供を始めた。北部ハリヤナ州グルガオンの日本食レストラン「くふ楽」で提供していたカレーうどんに対するインド人客の注文が思いのほか多いことに目を付けた。
外部のカレールウは使わず、すべて手作りすることで動物性原料を使用しないベジタリアン対応とした。玉ねぎやトマトに、野菜やハーブを煮込んで作った自家製ソースを加え、隠し味にチョコレートを加えることで、日本カレーのコクを再現している。
廣濵成二郎海外事業本部長によると、「日本式カレーは、すしやラーメンと同列に、インドのカレーとはまったく別ものの料理として、インド人に受け入れられている」という。同店で一番人気のカレーは香ばしく揚げたチキンかつを使った「クリスピー・チキン・カレー」。廣濵氏は「食に関してインド人の心をつかむキーワードはクリスピー(サクサク)、オイリー(油っこい)、スパイシー(辛い)の3つ」と話す。辛さを利かせたカレーに、サクサクに揚げたチキンかつを乗せたカレーはこうした条件をぴったり満たす。さらに、7月からは同じく3条件を備えたカレーパンの提供も始めた。
廣濵氏は、「これまで保守的と言われてきたインドの食文化だが、海外旅行をするインド人が増え、外国の食文化を受け入れる素地が高まっている。特に『日本食はヘルシー』というイメージが定着しており、日本のカレーが受け入れられる条件は整ってきた」と語る。
ラーメンなども提供するTOKYO TABLEの1カ月当たりの現在の売上高は100万円ほど。開店から1年後の来年1月ごろには7割程度の増収を見込む。今後は西部ラジャスタン州ニムラナや南部タミルナド州チェンナイで展開している他のレストランでも日本式カレーの提供を始める方針だ。
元祖レトルトカレーがインドへ
1968年に世界初の市販用レトルト食品として「ボンカレー」を発売した大塚食品。50年の節目となる今年、インド市場で同ブランドを発売することを決めた。今年5月に南部カルナタカ州ベンガルール(バンガロール)に現地法人「大塚フーズ・インディア」を設立し、今秋の発売に向けて準備を進めている。ボンカレーの海外展開は、2003年に進出した中国・上海に続いて2カ国目だ。
点滴の殺菌技術を食品加工に応用したレトルト容器を使うことで、常温で長期保存できるボンカレーは、「誰でも失敗なく作れるカレー」が開発当初のコンセプトだった。ボンカレーが発売された1960年代後半は、米国発の女性解放運動である「ウーマンリブ運動」の高まりから、女性の社会進出が顕著になっていた時期。母親が不在でも、父親や子どもたちが手軽に調理できることが最大のセールスポイントだった。
国内総生産(GDP)の成長率が対前年比7%を超え、高い経済成長が続くインド。女性の社会進出も加速しており、ボンカレーが発売された当時の日本の時代背景とも重なる。これまで「外国人も数多く集まる世界的なIT都市として知られるバンガロールのある南部を中心に、外国の新たな食文化を受け入れる素地も高まっていると判断した。
ベジタリアン向けに動物性原料の代わりに、インドで食用に用いられているバターオイル「ギー」やマンゴーなどをブレンドすることでうま味を確保する。現地のカレーとの差別化するため、独特のとろみは残す方針だ。日本のボンカレーをベースに、地域ごとの好みを加味した味わいとする。当面はインド南部を中心とした販売を計画しており、味付けも南部のカレーの特徴である酸味や辛みを意識しているという。
カレー総合研究所の井上代表は、ボンカレーのインド進出について、「老舗ブランドのボンカレーは、日本では一定以上の年齢の消費者が『昔ながらのレトルトカレー』として食べている。そうしたバックグラウンドのないインドでは、オリジナルの味にこだわらずインド人の好みに合わせられるかが成功のカギだ」と話す。「ハウス食品やエスビー食品などのカレーの大手メーカーでもインド進出の話はあったが、壁の高さから浮上しては消えていった。そういった意味でも、ボンカレーのインドでの成否が注目される」と付け加えた。
レトルトは非常食として活路?
ボンカレーのインド進出に関して、管理栄養士の今泉マユ子氏は、レトルト食品としての可能性に着目する。一般的なカレーに使われる牛肉の油脂は、融点が高く、熱を加えない常温のままでは固化してしまい、そのまま食べると舌触りがざらつく感じがするという。その点、ベジタリアン対応のため、動物性原料を使わないインドのボンカレーは、電子レンジや熱湯で温めなくてもおいしく食べられると考えられ、「非常用の備蓄食料としても有用」と分析する。
日常的にレトルト食品を多めに購入し、古いものから消費し、切らさずに買い足すことで常に一定量の食料を備蓄しておく「ローリングストック法」の重要性を強調する同氏。洪水やかんばつなどの災害が頻発するインドでも非常食としてのボンカレーの可能性を指摘した。