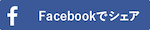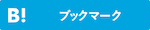「東西」の本から「亜州」を読み解く
アジアの本棚
『紙の動物園』
ケン・リュウが伝える“伝統的アジア”
前号で紹介した中国のSFアンソロジー『折りたたみ北京』の編訳者であるケン・リュウ(劉宇昆)は、現代の米国を代表するSF作家だ。代表作『紙の動物園』(原題:The Paper Menagerie)は2012年にヒューゴー賞、ネビュラ賞、世界幻想文学大賞のSF分野での3大賞を史上初めて総なめにした。
リュウは1976年に中国甘粛省で生まれ、11歳で米カリフォルニア州に移住したが、「中国系米国人」と呼ばれるのをあまり好まず、自分を紹介するときは「アメリカ人」と言うようにしている、と語っている。事実、彼の作品に出てくるのは中国系の人物ばかりではない。米国人や日本人もよく登場する(宇宙船に乗りこむ日本人青年が主人公の『もののあはれ』(Mono no Aware)は一例だ)。米国人の多様な価値観も備えているのだが、それでも、彼の内部に根差した中国文化が作品に独特な魅力を加えているのは確かだ。
圧倒的な評価を受けた『紙の動物園』はその代表といえる。米国で育った「ぼく」に、誰もが魔法を使える中国の農村出身の母は、折り紙で動物や魚を折っては生命を吹き込んでくれる。特にお気に入りだったのは、走り回ってほえたりする「老虎」だった。しかし、「ぼく」が10歳くらいになったころ、米SF映画『スター・ウォーズ』のおもちゃを自慢する米国人の友だちが「老虎」をゴミ扱いして投げ捨てる。それ以降「ぼく」は「米国的生活」になじむことを最優先して、英語のうまくない母を疎むようになり、紙の動物たちも屋根裏にしまい込んでしまうが…。
単に気の利いたSFというレベルではなく、弱く見える者が実は強い力を備えていたという古典的テーマを扱った小説であり、深い愛の物語でもある。
作品にはリュウ自身の経験も反映されていそうだが、私は清代の作家、紀イン(にちへんに匀)が奇談を記録した『閲微草堂筆記』に出てくる、年を経た人形が怪異を現す話を思い出した。小説ではなく、目撃した人から聞いた形を取っているが、『紙の動物園』と共通しているのは、人智を超えた存在と共存してゆく生き方だ。リュウ自身は大学卒業後マイクロソフトで働き、その後ハーバードのロースクールを出て、現在は特許訴訟専門の弁護士という「米国的生活」を具現した人生を送っている人だが、そうした作家が18世紀の中国人が感じていたのと同様な超自然的な感覚を再現しているのは非常に興味深い。
リュウはデジタルメディア、WIRED日本版のインタビューで「中国や日本の歴史的建造物や農業技術を見ていると、自然の力をうまく生かしているが、いまの中国はその考えに沿わない方向に発展が進んでしまった。だからこそ、伝統的なアジアの考え方を伝えたい」と語っている。リュウはまた、『月へ』という作品で「だれもが物語を持っている。だけど、あなたたちはある種の物語しか聞きたがらない」と書いている。自分が慣れ親しんだ(絶対的に見える)価値観にとらわれ過ぎてはいけない、というのが多文化的背景に持つ作家が発信し続けているメッセージだと思う。
『紙の動物園』(ケン・リュウ短篇傑作集1)
- ケン・リュウ 早川書房
- 2017年4月発行 680円+税
【本の選者】岩瀬 彰
NNA代表取締役社長。1955年東京生まれ。慶應義塾大学文学部を卒業後、共同通信社に入社。香港支局、中国総局、アジア室編集長などを経て2015年より現職