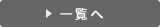最新情報
【祝】「The Daily NNA シンガポール版」2000号特集
《寄稿》早稲田大学 大学院 アジア太平洋研究センター教授 小林英夫
シンガポール日系企業の今後――対中交渉ヘ切り札の地位

「温故知新」、この言葉にはすべての真理が含まれている。シンガポール日系企業の将来を考える時もこのことわざはあてはまる。そんなわけで、シンガポールの今後の見通しを予測するためには、まずもってこれまでの道筋をたどってみることが必要だ。したがって、これまでのシンガポールへの日本企業展開の歴史を素描することからはじめることとしよう。
戦後の日本企業のシンガポール進出の歴史は1960年代に本格化する。1960年代シンガポール政府は一連の政策を施行して外資企業の誘致に乗り出したからである。シンガポール政府は1960年代に島の西南部にジュロン工業団地を開設、同時に第一次、第二次経済開発計画を立案、経済開発庁(EDB)の指導の下で外国企業の誘致に努めはじめた。さらに67年には「経済拡大奨励法」を制定、外資に各種の特権を与えて工業化に乗りだしたのである。一連の工業化政策、投資誘致は東南アジア諸国のなかでは先駆的部類に属する。
こうした投資環境の整備の結果、シンガポールに外資系企業が殺到した。日系企業も例外ではなかった。1972年には折からの日本の円高の開始の中で日本企業の東南アジア進出が始まり、78年、85年の2度の円高の更新の中で、日本企業のシンガポール進出は加速度化された。
筆者がはじめてシンガポールを訪問したのは今から30年前の1972年のことであるが、当時はまだ戦前のおもかげが街の随所に残っていた。その頃はジュロン工業団地が開設されて日も浅く、日系重工業企業がひしめき、ジュロン・シップ・ヤードには大型船がドック入りしていた。当時この会社の日本側のジョイント・マネジング・ダイレクターだった桜井清彦氏の流暢な英語と絶えざる笑顔を今もなつかしく思い出す。
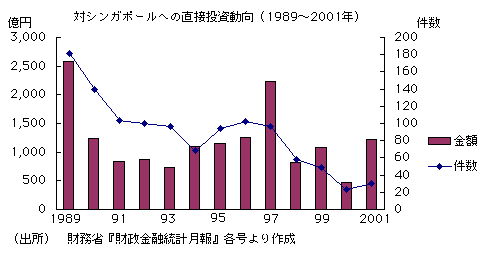
日本企業の進出業種も時代により変化してきた。1970年代の日系企業のシンガポール進出の主力は、この国がかつて中継貿易地であったこととも関連して、サービス・貿易・商業・運輸・倉庫が大きな比率を占めていた。しかし、80年代に入るとこうした特長は失われたわけではないが、電子産業の比重が高まると同時に、東南アジアのハブ的機能を果たす産業がしだいに大きな割合を占めはじめたのである。90年代以降は、金融・通信・中継貿易・ハイテクの基地として文字通り東南アジア諸国のハブ的機能を果たすことが期待されている。日系企業もまた、そうした機能と役割を担って金融・通信・ハイテク企業がシンガポールへ進出してきているのである。
しかし、1990年代後半以降アジアでの中国の台頭と躍進、中国の経済的役割の増加の中で、シンガポールの役割にも少しずつではあるが変化が生まれはじめてきている。中国と日本と東南アジア、この3つの地域をリンケージする1極としてのシンガポールの役割の増大である。2002年1月、日本とシンガポール政府の間で締結された「新時代経済連携協定」はその役割を実施していく第一歩と考えることができるだろう。また中国政府もシンガポールを含む東南アジア諸国との「自由貿易協定」の実現を模索し協議を続けている。上記のような近年の東南アジア地域に生じた一連の動きを考慮の中に入れると、日本―シンガポール―中国を結ぶ太いリンケージが近い将来できあがるであろうことは疑いない事実である。
しかし現実の日本企業の対東アジア投資額の動向をみると対中国投資は増加の一途をたどっているが、日本企業の対シンガポール投資は減少傾向をたどっている(前ページ図参照)。1990年139件、1,232億円だった日本対シンガポール投資は94年には69件、1,101億円に減少し、さらに2000年には23件、468億円とボトムを記録した(『財政金融統計月報』より)。
つまりは90年代から2000年初頭にかけて、他の地域同様、日本の対シンガポール投資は減少の途をたどっているのである。それはゆえなきことではない。表をみていただきたい。これはアジア各都市の賃金・事務所賃貸料・インターネット接続料・TOEFL平均点数・IMD(スイスの経営開発国際研究所)のランキングを調べたものである。中国の上海と比較するとシンガポールの投資条件は決して優位にはない。それゆえに多くの企業は中国への投資活動を強めているのである。
しかしこの間、シンガポール進出企業が地域の意思決定機能を有し、東京にその機能を返さないまでになり、確固たる地位を築いたこと、その反面でこれまでシンガポールと競い合ってきた香港の落ち込みが顕著となったこと、この2つの条件を考慮すると日・中・星リンケージ形成に持つシンガポール機能の重要性が浮き彫りになる。そのように考えると、現在の日系企業の対シンガポール投資の減少は好ましいことではないし、再考を要する課題だと言わざるを得ない。
中国市場の有望な将来性については多言を要さないであろうが、しかし中国への全面的な投資は危険な賭け以外の何ものでもないことを留意する必要がある。むしろ中国と東南アジア投資は同じ比重になることが望ましい。そうすれば、この比重が、日系企業にとっても中国との交渉を進めるうえで「切り札」となるからである。最近日本の財界団体もこの事実に気づき、改めて東南アジアの重要性を認識し、投資増加に向けた具体的対応に動き始めたと聞く。筆者もまったく同意見で、中国と東南アジアのバランスの上に日本企業のアジア展開の要諦があることを再認識する必要があろう(この点詳しくは拙著「産業空洞化の克服」中公新書2003年3月参照)。
日本―中国―シンガポールのリンケージ形成に際し、東南アジア諸国連合(ASEAN)内でシンガポールがかなめの位置に就きうる理由は、IMD世界12位という数字に表現されるその高い教育水準にある。確かに周辺諸国と比較するとシンガポールの賃金は高い。製造業なら、より付加価値のある業務でなければ生き残れない。しかしその高い教育水準ゆえに周辺諸国にはできない高付加価値の業務が可能なのである。この事実こそがシンガポールをして日・中と並ぶアジア3極の1極を構成できるゆえんであるし、シンガポールの日本企業の今後の一層の発展が期待される理由なのである。
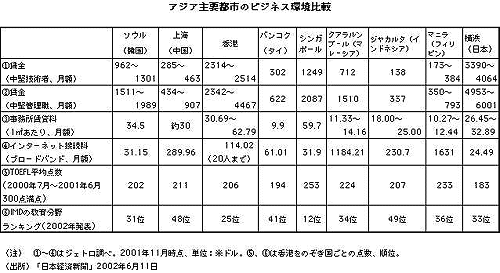
【筆者略歴】
1943年東京生まれ。71年、東京都立大学大学院社会科学研究科博士課程単位取得退学。駒澤大学教授等を経て、96年より現職。主要著書は『「日本株式会社」を創った男――宮崎正義の生涯』小学館、『日本企業のアジア展開』日本経済評論社、『戦後アジアと日本企業』岩波書店など。